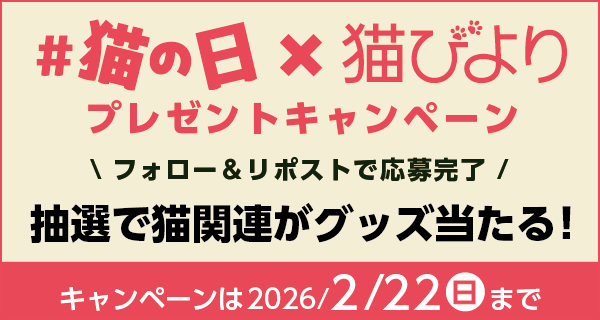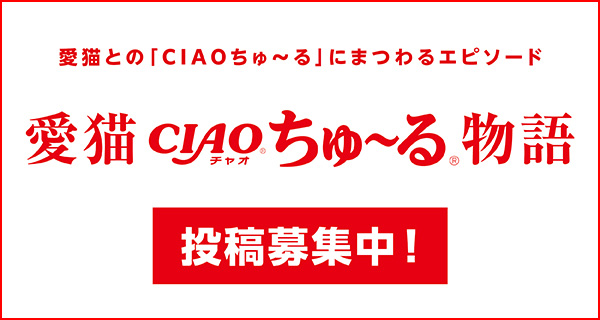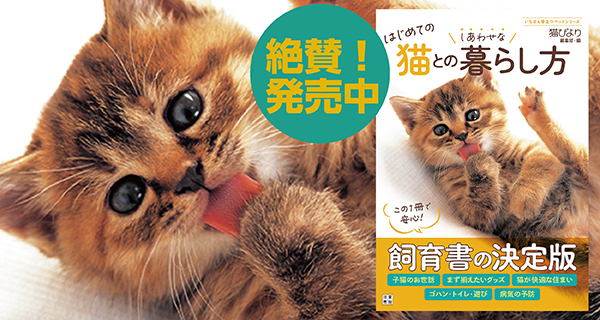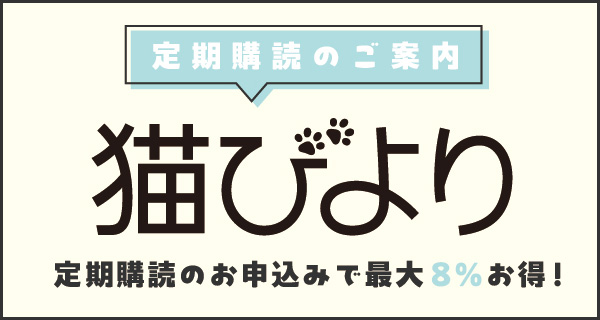約17年間、フレックス動物病院にお世話になった我が家のボンビ(♀)。
今月9月に虹の橋を渡る前日まで影踏み遊びをしていました。
1987年に開院した大阪市北区の「フレックス動物病院」が目指しているのは、地域のホームドクターとして、ペットと飼い主さんが無理なく通える病院だ。會田(あいだ)裕子院長、藤村菜苗獣医師、羽渕真由美獣医師の3人の獣医師は診察の際に、雑談も交えながらより詳しく飼い主さんの話を聞く。さまざまな話を通して、飼い主さん自身が気付かなかったこともあれば、多くの情報を共有することで、治療の幅が広がるからだ。

同居猫テンテン(3歳♀)の振る舞いもいつもと変わらずマイペース
早期発見の可能性を高めるため、健康診断は7歳前後になった頃から勧めている。しかし高齢猫が体調不良で久しぶりに来院したときは、視診、触診、聴診、エコーやレントゲンでは原因が特定できないことも多い。麻酔をともなうCTやMRIは検査の時点で、すでに体調が悪い高齢猫には大きな負担がかかる。

ボンビがいなくなってすこし寂しげにも見えたテンテン。でも数日も経つと、新しい生活に慣れたのは、日常が激変したとは感じていないからかも?
高齢猫の治療は猫、飼い主さん、獣医師の三者がチームになってケアすることが基本だ。だが猫の性格、飼い主さんの考え方、ま
た猫の治療に割くことができる時間や経済力は千差万別。どこまでの治療が猫にとっても飼い主さんにとっても負担にならず、QOLが保てるかという目安はない。ただ自宅でも猫と暮らす羽渕獣医師は言う。
「猫が少しでも自らの口で食べて飲もうとするのは、とても大切です。食べようとする意志と意欲を尊重することが、猫の生きる
力を後押しします」。
そして會田院長は一例として、19歳で腎臓の数値が悪くなった猫を挙げてくれた。「いろいろな療養食を試してもらいました。でも飼い主さんの最終的な判断は、『もうすぐ20歳なのだから、いつまでも好きなものを美味しく食べてほしい』でした」。療養食の方が良いと言っても、まずは食べてくれることが大前提だ。

會田裕子院長(右)と羽渕真由美獣医師。獣医師歴が長いからこその常識的で優しい説明は、我が家も含め飼い主さんを説得し落ち着かせてくれます
また治療を進めていく中で、飼い主さんの当初の「してあげたい」という積極的な気持ちが、徐々に「しなければ」というプレッシャーへと、精神的に追いつめられる場合もある。會田院長は、「猫に『治療のためだから頑張って』と言い聞かせることはできません。ただ飼い主さんのQOLが下がることは、ひいては猫にも少なからず影響はあるでしょう。高齢猫医療では、コミュニケーションがより重要だと思います」と話す。

我が家の最初の猫テンコ(右・♀)とボンビ。猫から猫へのリレーのような関係も、家族としての雰囲気を醸すのだと感じます(2021年2月撮影)
ところで食事やトイレ以外に、一緒に暮らす猫からの簡単な健康サインがあるという。それが関節炎。高い場所に上らなくなった、上っても降りることを躊躇(ちゅうちょ)するようになったのは「もう、年だから…… 」と見過ごされがちだが、関節炎も疑われる。最近は猫の関節炎に「ソレンシア」という薬がある。ソレンシアは従来の鎮痛剤(非ステロイド系消炎鎮痛剤)に比べて副作用が少なく、腎臓への負担もかからないことから、高齢猫への長期投与が可能だ。注射薬ゆえ通院の負担はあるものの、月に1回程度なので、毎日服用させる手間はない。
「とくに高齢の猫にとって、普段と変わらない生活は何より大切で幸せなことだと思います」
無駄な検査や治療は省き、猫、飼い主さんにとって良質な生活をより長く。それがフレックス動物病院のぶれない方針だ。
(文・写真 堀晶代)
Hori Akiyo
日仏を往復するワイン・ライター。著書に『リアルワインガイド ブルゴーニュ』(集英社インターナショナル)。電子書籍『佐々木テンコは猫ですよ』がAmazonほかネット書店で好評発売中。

フレックス動物病院
大阪府大阪市北区本庄東2-2-2 1F
TEL 06-6375-8555
https://www.flex-ah.com